|
あのひとに出会ったのは結婚を間近に控えた大正六年の春。 あのひとが逝ったのは大正十二年の夏。関東大震災であのひとは逝った。 六年半。 長くはない。 けれど短くはない。私たちの幸せだった時間。 千尋に憎まれ、父母に、親族に蔑まれた六年半。 私はあの時間があったからこれまで生きてくることが出来た。 嗤いたかったら嗤うがいい。 私はただ、あのひとの思い出だけを糧に生きてきた。 他の誰でもない。 妻でも息子達でもない。 あのひとの思い出だけが私を生かしてきた。 期間にすれば短い幸福の記憶と、扶養する家族への義務感。 ただ、それだけだった。 だからあのひとが逝った夏の日、私も共に死んだのかもしれない。 そうでなければどうして冬樹の生まれるはずがあろう。 私は生きて、まだ周りを不幸に陥れている。 そうでなければどうして夏樹が千尋に殺されかかったりするものか。 彼女は知っているのだ。私の心に棲むのがただ一人であることを。この世にいなくとも私が愛したのはただあのひとだけであることを。 千尋は千尋なりに私を愛していたのかもしれない。 結婚間近にして婚約者を奪われれば憎みもするだろう。 いずれにせよ私には遠い話でしかない。 私には今なお、あのひとしか見えない。 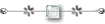
「夏樹、目を悪くするよ」 そっと肩に置かれた手でようやく真人の気配を知った。 気づけばあたりは暗い。 革表紙の本に手を置いてじっと考えていた。 どれほどそうしていたのか、定かではなかった。 父の几帳面な字でびっしりと書かれたそれはあっさりと読むにはあまりに重く、鬼気さえ漂っていた。 咀嚼しきれない固い物でも噛むように何度も何度も一文を読み返し、読み直し。 とうとうその分厚い日記帳を閉じて俺は思いの中に沈みこんでいた。 読んでなどいないのだから目が悪くなるわけもない。 この張り詰めた気持ちを察してくれる真人の存在をいまほどありがたく思ったことはなかった。 「父は……」 「うん、お父様がどうしたの」 おっとりと微笑う真人に、俺はなにを言うつもりだったのだろうか。 「いや……」 それだけを言って顔を伏せた俺の髪を真人がそっとひと梳きしていく。 体の中によどんだ重たいなにかを拭い去るかのように、そっと。 「晩御飯にしようよ、夏樹」 目で、口元で、全身で。 なにも心配する事はない、とでも言うように真人が笑う。 「今日は暑かったからねぇ、冷奴でちょっと飲まない」 そのくせ、なにも聞かない、なにも言わない。 真人は再び笑って台所に行ってしまう。 逢えてよかった。しみじみ思う。 父が愛したひとはいったいどんな人だったのだろうか。 どんな風に愛し、愛されたのだろうか。 ああやって書いたほど、幸せだったのだろうか。 幸福だ、そう父が繰り返し書けば書くほど、とてもそれが本心とは思えない。 もっともだろう。 父が書いたことが本当ならば、誰も彼もを敵にまわして手にいれた唯一の恋人を父は失っているのだから。 その答えはこの日記帳の中にあるとわかっていても、とても流し読みにすることなどできなかった。 寝苦しい、というわけでもないのに輾転反側する。 理由はひとつ。 あの手記。 容易に噛み砕ける感情ではないものを抱え、上手く寝付けなかった。 隣で眠る真人の規則正しい呼吸を聞いているうちに、普段だったら眠れるものを今夜はどうにも寝付けそうになかった。 真人を抱きしめたら気持ちが静まるだろうか。 いや。 起こさないようそっと抜け出し居間に戻った俺の手には父の手記があった。 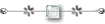
あのひとは剣持薫、といって私よりみっつ年上。 皮肉か、運命だったのか千尋の母方の従兄だった。 千尋は私との長い結婚生活の間、ずっと悔やみ続けた事だろう。 私たちを会わせたのは彼女だった。 もうすぐ結婚式だ、というあれは春まだ浅いころだった。 「従兄を貴治(たかはる)様のお目にかけたいの」 確か彼女はそう言って私たちを引き合わせたのだ。 兄と慕う秀麗な従兄のことは聞き及んでいたが、会おうと思ったのはおそらく私がこの許婚にいくばくかの愛情めいたものを感じていたからだろう。 後にそれは許婚だから愛さねばならない、という強迫観念からきた全くの誤解だった事に気がつくのだけれど。 気がつきさえしなければ、彼に会いさえしなければ。 いや、くだくだしく考えるまい。 私が彼女を不幸にした、その事実はすでに定まって変わらない。 千尋に伴われて訪れた剣持家はどこか質実剛健な武家の風を残した、私にとっては非常に居心地にいい屋敷だった。 訪問を約束してあるにもかかわらず、私と千尋は客間に通されない。 勝手知った従兄の家をすいすいと進んで行く彼女に黙ってついていくとそのまま庭に。 遅咲きの白梅がぷん、と香るのが心地よい。 今でもあのときの景色が、匂いが、くっきりと浮かぶ。 空は遠くまで澄み切って、ちらほらと浮かぶ雲がそれは綺麗な模様を作っていた。 冷たい空気に口元からちいさな雲が浮かぶ。 作り込みすぎない、けれど美しく手入れされた剣持の家の庭。 敷き詰められた白砂が足元でさくさく鳴った。 清冽な墨絵のような庭。 ただ梅の香だけが色を添えている。 あのひとはその白梅の古木の下に立っていた。 洋装流行の昨今にめずらしくも着物姿で対の羽織をまとい、軽く腕を組んでは目を閉じていた。 「やっぱりこちらにいらしたのね」 千尋の声にゆっくりと目をあけて微笑んだ彼。 「この季節のお兄様は梅狂いでいらっしゃるのよ」 私に言ったのだろうか。 声は遠く、現実感はなかった。 世界から取り残されたように聴覚が音を失い、目はただ梅の古木とあのひとの姿だけを鮮やかに浮かび上がらせた。 失調しかける意識を保とうと腹に力を入れて少しだけ目を閉じる。 ほんの一瞬だったのだろう。 目をあけたときあの人はまだ微笑んでいた。 |
モドル ススム