|
父が逝ったのは五月の空が遠く澄んだ日のことだった。 そして相次いで母も死んだ。 父を憎み、俺を憎みぬいた母。 父の死によって張り詰めていた気持ちがふっつりと切れたような死だった。 葬儀は当然、弟が喪主を努め、俺はどちらにも一介の親族として参列しただけだった。 ひっそりと横たわる父の体。役目から解き放たれたような静謐な顔。なぜ、というわけでもなく触れた頬はまだ幾分のぬくもりを残していて、わけもなく涙があふれ、そのことに俺が一番驚いたものだった。 母には触れもしなかった。最期の対面をすることもなかった。 ただ、弟の体面を考えて葬儀に出席した、それだけだった。 それだけの事を俺はこの母にされたのだ、この期に及んでそう考えた自分が少し、哀しかった。 弟が、冬樹が俺の住まいを訪ねてきたのは四十九日も済んだ夏の日。蝉の声がかしましい日だった。 母に似たほっそりとした女性的とも言える顔立ち、けれど目は父によく似た。 諦めと達観と、そんな目の色かもしれない。 すべてを押し付けて出奔した俺が罪悪感を抱くのは、彼に優しく微笑いかけられたときだった。 いつも冬樹は柔らかく笑う。 母親の事は任せておけばいい、とでも言うように。 母が死んでも彼はやはり、そんな風に笑って俺を見ていた。 「父上の遺品を整理していたら、こんなものを見つけて」 俺の家の居間にゆったりとくつろいで、冬樹は言う。 真人が淹れた冷たい麦茶をひとくち飲んで、それからたずさえてきた一冊の本を出したのだった。 「これは」 尋ねる俺に 「父上の日記……覚書……いえ、兄さんへの長い、長い手紙……なのでしょう、きっと」 遠い目をした。 「私は父上には愛されなかった。代わりに母に溺愛された」 考えるように一度、彼は言葉を切り、そして続ける。 「それが不幸せだったとは思いません、でもこれを少しだけ読みましたが……兄さんがうらやましい」 そっと厚い本の皮表紙の上、手を置く。まるで父その人に触れるかのように。 「父上にとって息子は兄さんひとりだった。私は……」 口を閉ざした弟に、俺はいったいなにが言えただろう。 「贖罪の行為が愛した、と言うならば、そうかもしれない」 喉からしぼり出た声は自分で思うよりなお固かった。 それに冬樹は微笑ったのだ。 あの、痛々しいほどの透明な笑みで。 軽く目を伏せ、それから庭を眺めた。 庭など見ていなかったのだろう。 なにかに戸惑う表情を浮かべ、そのままじっと考え込む。 その間も手はずっと書物の革表紙を撫でていた。 冬樹が口を開いたのはずいぶん経ってからだった。 「はじめの方を少しだけ、読みました。私にはとても読みきれない。兄さんに宛てたものだから、というより父上の生涯があまりにもつらすぎて、私には読めない」 「これには、なにが」 おかしいほど自分の声が震えている。 知りたくないことを知らされる、そんな恐怖かもしれない。 あの父がなにを考え、なにを思い、そしてそれを知らせようとはせず死んで行った。 知るべきではないなにか。 漠然とそんな予感がする。 いや、予感、ではなくただ恐怖しただけなのだろう。 それを悟ったかのように冬樹が言う。 珍しいほどのきっぱりとした口調で。 「兄さんは読むべきだと思う。私が半端に口にするより、読むべきだと思う」 静かに目を閉じたのは父の姿を思い出しているのか。 妻に強烈に憎まれた父。 息子を妻の害意から守ることもできなかった父。 淡々と生きているだけだった。 家には居着かなかった、父。 遠くかすんでもう、いない。 「父上は……幸せだったと、思いますか。兄さん」 そう、最後に言って弟は帰っていった。 答えることができない、問いを残して。 幸せだったはずなどありはしない。 けれどその人生をただそんな一言で否定してしまいたくもない。 これを読むことが亡くなった父への、せめてもの手向けになるのならば。 そんな気持ちで革表紙を、開いた。 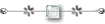
許して欲しい、などと言うつもりはない。 許される、とも思っていない。 夏樹に知って欲しいと思って書くのでもない。私はただ、自分のためにこれを書いている。 あのひとのことを鮮明に、鮮明に思い出したい。 なにひとつ忘れてはいないあのひとのことをより鮮やかに、くっきりと思い出したい。 出会ったのが間違いだったのか。それがすべての原因だったのか。 あのひとに出会い、私ひとりが幸せだった。 妻も息子も周り中、誰も彼をも不幸にして、ただ私だけが幸せだった。 いやせめて 「私たちだけが幸せだった」 と言いたい。 あのひとは幸福だったはずだ。 私が感じた幸せと同じくらい、あのひともそれを感じてくれていたはずだ。 今となっては確かめる術もないことだけれど、それだけは確信している。 だから余計に周りを不幸にしたのだ。 時間が経った今なお私にとって最大の、そしてたったひとつの幸福はあのひとでしかありえない。 私がこんなに酷い人間であることを誰かに告げられようか。 なにも知らずに、彼の罪ではないのに殺されかけた息子にこれを告げられようか。 口が裂けても許して欲しい、などと言えるはずがない。 そもそも許しを請う気など毛ほどもない。 私もあのひとも悪い事などしてはいない。 ただ、出逢ってしまった。それだけだ。 読ませるつもりもない息子にここで告げるのもおかしいけれど、私は幸せだった。 私は本当に幸せだった。 決して夏樹よ、お前が思うほど不幸せだったわけではない。 むしろ不幸のどん底にいたのは、お前の母親だった。 私たちが仮に許しを得なければならない人がいるとするならば、千尋ひとりにだろう。 少なくとも私は確実に彼女を苦しめたのだ。 だからといって彼女が、千尋がお前を殺そうとした事の償いになるわけでもなく、私がそれを止め得なかった事への贖罪になるわけでもない。 悪いのは私なのだ。 すべての原因を作り、ひとり勝手に幸せを貪った、私なのだ。 |
モドル ススム 外伝トップに