|
大正十二年九月一日。 私はおかしなことに屋敷にいた。薫さんの待つ日ノ出町の小さな家ではなく、愛情など通いもしない妻のいる屋敷にいた。 正午少し前だった。 朝食を妻の給仕で済ませた時になにかいやな気がしたこと覚えている。 千尋は私がいようと自分の部屋から出てくることはまずなかった。 いや、かえって私がいるからこそ、姿を見せなかったのかもしれない。 その方がお互いの為である、と何年かの生活で二人とも学んでいた。 だからその日、千尋が給仕した朝食、と言うのが空恐ろしくあったのだ。 屋敷にいても薫さんのことばかりを考えていた。 「たまには子供の顔を見ておいで」 前日そう言っては笑い、彼は私を送り出した。 質素で小さな家。 三部屋ばかりの家の壁はなににかわからないもので煤けていた。 申し訳程度の庭はそれでも薫さんが好んだ花木が少しばかり植わっている。 この庭の手入れも薫さんが――と思えばやりきれなく、温かく迎えてくれる想いのほどに感謝する。 そんな小さくとも私にとっての温かい「家庭」からなぜ屋敷に戻ろうとしたのか。 彼が奨めたから、と言ってもいまでも私は後悔している。 そう、正午少し前だった。 千尋がまたも顔を見せ、昼食はいかがしますか、と冷ややかに尋ねたのに輪をかけた声で私はただいらない、とだけ答えて。 そして轟音がした。 いや、音ではなかったかもしれない。 下から突き上げるような凄まじい揺れを一瞬地震だ、とは認識できなかった。 悲鳴、怒号。それらがたちまち辺りに満ちて静かな屋敷の中が信じがたい混乱に襲われた。 平衡を失った私も無様に膝をつき、どこかに逃れなくては、と思った時にはまた大きな揺れに襲われた。 「薫さん……薫さんが……っ」 思うのはそれだけだった。 妻の事など思考に登るはずもない私の目にとまったのは。 夏樹だった。 倒れてきた椅子に頬を傷つけられ、血を流すお前に誰一人構っていない。 遠く、視界の隅に千尋が大勢の使用人に囲まれて慄いているのが見えた。 捨てて行けようか。 夏樹は泣くでもなく声をあげるでもなく、目を見開いてじっと私を見ていた。 大地は収まるところを知らず、咆哮をあげ続けていた。 這い寄った私にしがみつく小さな手。 泣きもせずにお前はただ、指先だけで私にすがっていた。 そのとき私が薫さんのことだけを考えていたか、といえば嘘になる。お前の事だけを労わっていたか、と言えばさらに嘘をつくことになる。 夏樹を抱いたこの腕で、私は心の中に薫さんを抱いていた。 刻々と知らされる被害の大きさ、そのたびに顔が青ざめるのを自覚した。 時機を逸した私は屋敷から出ることあたわず、錯乱状態の千尋の元に夏樹を置くことへの漠然とした不安もあり、結局屋敷を出ることができたのは三日を過ごしてからだった。 町は未だに煙を吐いていた――。 荒んだ目、呆然とした目。 見るでもなく私を見る人々は煤に汚れ傷を作り座り込み、あるいはせかせかと働く。 知らず足が鈍った。 恐怖。 屋敷に止められている間にもしも。 そう思うだけで両の足が震えた。 酒に酔ったように私たちのちいさな家に踏み込めば――。 姿はない、薫さんはいない。 探した。私は探した。 部屋の隅々まで、いや湯殿の中までも探した。心のどこかで答えを知っているかのように、必死で。 誰の声も聞くものか、と。 それなのに、声は聞こえるものなのだな。 「ここの人の知り合いかね」 頬に汚れをこびりつかせた中年の女が立っていた。 程よく太ったその女は混乱から抜けて身奇麗になればきっと明るい家庭婦人なのだろう、と思わせるものがあり、そんな事を考えた自分が不思議だった。 ただ、聞きたくなかっただけなのかもしれない。 「ここの人ならね、地震で亡くなったよ。一昨日だったかね、親戚だって人が来て遺体だけ持って帰ったよ」 目の前が暗くなる。なにかを喚きたてている自分の声が聞こえる。 なだめる女の声。畳に打ち付ける拳の音。 頬が熱くなって正気に返った。 「しっかりおしよ」 仁王立ちした女の剣幕に押されてみればどうやら頬を殴られたらしい事だけは理解した。 それから女は私が尋ねたと気付かず喚きたてていた事に順序良く丁寧に答えてくれた。 薫さんが地震で亡くなったこと。 家はしっかりした造りだったから倒壊は免れたものの、庭側の隣家から火が出て逃げ遅れた彼はおそらく煙に巻かれたのだろうこと。 「だからね、ちらっと見た限りじゃご遺体はきれいなものだったわよ」 慰めるように女は言った。 ぼそぼそと礼を述べる自分の声。またも私は失調していた。 気付いた時にはもう女の姿はなかった。 日が暮れたのかあたりは薄暗い。呆然と焼け焦げの残る塀を眺めていた私は過ちに気付く。 夜明けだった――。 夜は、明けるのだ。 こんな時にも、日は昇るのだ。 薫さんのいないこの世に、朝がくる。 信じられるわけもなかった。 薫さん、私の薫さん。つい何日か前に別れた時には笑顔で送り出してくれた薫さん。あの時に言う事など聞くのではなかった。助けられたかもしれない。助からなくとも一人で死なせたりせずに済んだ。体を望まない家族の元に連れ去られる事もなく、私は――。 泣けもしなかった。 自分、という存在が希薄になってどこか遠くから自身を眺めてでもいるような気がした。 ふらふらと家中を彷徨った。 ちいさな私たちの家。 薫さんが覚束ない手で作ってくれた食事。 慣れない洗物に欠いた茶碗。 倒れた食器棚に押しつぶされていまはもう、ばらばら。 震えた手で触れたならば指先からは血が流れ。 痛みを感じはしなかった。 この血を流すように、泣ければいい――ただそう思っていた。 薫さんの着物。 埃まみれの着物。抱けばまだ薫さんの匂いが、した。 後で聞く。 死者・行方不明者は十四万二千八百名を数え全壊した建物は十二万を超え、焼け崩れた建物は四十四万七千棟――。 それが関東大震災、と呼ばれた地震の被害だった。 だからなんだというのか。 多くの犠牲を出し、多くの人が住む場を失った。 それがなんだというのか。 例え百万の人が死のうとも薫さん、たった一人薫さんに生きていて欲しかった。 私はただ一人の家族を恋人を家庭を、失った。 生きていた。 あの日薫さんの言う事に肯いたばかりに、生きていた。 呆然と過ごすうち、家のものがやってきて 「剣持家にて葬儀が執り行われました」 そう言って去って行った。 他にもなにか言っていたのかもしれない、私は覚えていない。 剣持家の葬儀、と言うのが他ならぬ薫さんのものであることだけ、それだけを理解した。 私は取り残された。 いったい何日そうしていたのだろうか。 薫さんが眺めた庭。 彼が座したその場所に、ただなす術もなくうずくまっていた。 夜が明け、暮れ、また明け。 暮れては明け、暮れる。 待っていれば帰ってくる気がした。 「帰ってたのかい、貴治君」 振り向けば彼が笑ってそこにいる気がする。 音のしない、火の気のない家の中。 私は待っていた。 「馬鹿だね」 薫さんがそう叱ってくれるのを待っていた。 ――帰ってくるはずのない家の中で。 狂いかけた私をもう一人の私が見ている。 「薫さんが帰ってきたら怒るじゃないか」 私は家中の掃除をはじめた。 彼がしていたように几帳面に。 倒れた棚は元のように。壊れた食器はまとめて箱に。 埃ひとつ逃さぬように、整然と。 彼の着物からほこりを落とし畳む手に涙が――。 着物に残る彼の残り香。 もう、帰ってこない。 ようやく受け入れた私は、あれからはじめて、泣いた。 私は、半身を、失い。すでにあの瞬間から、私の人生は、余生だった。 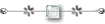
泣いていた。俺は泣いていた。 父が不憫だったのではない。その人生の一瞬があまりにも幸福であったそのことに俺は泣いた。 父は幸福な人だった。 断言できる。 「父上……あなたは幸福な方だ……」 指先で撫ぜる革表紙にぽたぽたと涙が落ちて染みになっていく。 こんなにも愛した人がいた。こんなにも一人の人に愛された。 これを幸せ、と言わずになにを幸せと言うのだろう。 父はいまの俺を見たらなにを言うのだろうか。 いや、おそらく真人のことは知っていたのだろう、そんな気がする。 父らしいやり方――黙殺する事で俺たち二人が母から害されるのを父なりに防いでくれたのだろう。 「父上……お父さん……」 愛されていたのですね、俺は。あなたなりに。 震災の日に俺の手を振り解いていけば恋人を助けられたかもしれない、それなのにあなたはただの一度も俺を責めたりはしなかった。 手記の中でさえも。 お父さん――。 生前にそう呼ぶことができたなら。 語り合う事ができたなら。 もう――いないのですね。 「お父さん……俺も幸福です……」 あなたのような父がいたこと。真人に出会えたこと。そしてあなたがこの家を――恋人とあなたが過ごしたこの家を残してくれたこと。 俺はこんなにもあなたに愛された息子だった。 知らずにいた。謝る事はもう、できない。 革表紙の手記、これだけが父と俺とを結ぶ細い親子の情。 父その人に触れるかのように手記を抱いた。 最期に触れた頬の温もりが思い出され。 本の皮を指先でなぞった。 その表紙に落ちた一葉の、写真。 「……」 声もなく見入った。 若き日の父と秀麗な青年。 盛装した二人。椅子に腰掛け堂々と微笑む青年の肩に手を置いて父が立っている。 父も微笑っていた。 見たこともない、幸福そうな顔をして。 色褪せた写真。父はこの写真を拠り所に生きていた、夢の中で、余生を。 「剣持薫……さん」 父が愛した人の名を唇に上せば写真の中のその人が微笑んだ気さえする。 裏を見ればそこには美しい手蹟で一言 「貴治君と。大正十二年、新春」 後日、真人が言った。 「お施餓鬼に、行こうよ」 お盆も近いことだし、と。 「露貴さんを誘えばたぶん……剣持の家のことも、わかるんじゃないかな」 そう言ってくれた真人。父とその恋人に手向けるものがあるとすればきっと、それは真人の言葉であるに違いない。 露貴が探し出してくれた剣持家の墓前で、そして父の眠る墓で、頭を垂れる。 どうぞあちら側で二人、幸せに。 期せずして真人と二人、空を見上げる。 「暑いね、夏樹」 晴れ渡った空に鳥影が過ぎる。 「あぁ、暑いな」 「かき氷、食べていこうよ」 笑って手をひく真人のその手をしっかりと握った。 つないだ手を離さず、歩いていく。 立ち止まってもう一度空を見上げ 「薫さん、父をよろしく……」 微笑んで見ていた真人に照れくさそうに夏樹は笑い、再び歩き出す。 二人の背中を押すように、風が吹きぬけて、行った。 |
モドル オワリ