|
淡々と綴られているのに薫さんの字は「跡取」と書くたびに震えていた。 私が千尋に触れ、子供を儲けることを想像せずにはいられなかった薫さん。 いとおしく、哀しい。 少しばかり線の細い、美しい薫さんの字を私は何度も指でたどった。 薫さんその人に触れているような、そんなつもりで。 いつのまにか姿を見せた使いの男に私は一も二もなく肯き、それだけで了承したのか男もまた肯いて去って行った。 薫さん。 薫さんはそうして、地位も名誉も失う事になった。彼の手の中に残ったのはただひとつ、私だけ。 それさえもその時点では傍らにない。 私の禁足はついに式の当日まで解かれることはなく、薫さんの「探すな」の言葉に逆らいたくとも逆らえない有り様だった。 淡々と進められていく式に、披露の宴に、他人事のような感想しか持てない。 「結婚」という形を望んだ千尋さえも私の心がどこにあるかをすでに心底、飲み込んでいるのだろう。冷たい目が遠くを見ているのみだった。 双方の母親だけがほっとした顔をしている。 形式に持ち込んだことで安心しているその姿が哀れでならない。 しかしそれさえも他人の感慨だった。 夜、千尋は言った。 「貴治様に触れられとうございません」 横たわり、厳しい目をして言った彼女を私は。 ――陵辱した。 そして夏樹が生まれた。 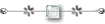
憎まれて当然だ。 俺は痛む額に手を当てる。 母を許す気になどなれはしない。けれど俺を憎むその「理由」が母にはあった。 許婚を奪われた母。傷つき頑なになった母を自分勝手な理由で、蹂躙した父。 憎まれて当然だ。 今更――今更この年になって 「生まれてきた理由」 だの 「生きている意味」 だのを問う気にはならない。 誰に望まれなくとも俺はここにこうして生きている。 けれど。 勝手に産んで勝手に憎んだ。 そう思っていた母がある意味では一種の被害者であった事を知ったいま、わずかばかり心が揺れる。 「父に似ている」 ただそれだけで憎まれた。 ずっとそう思っていた。 そう思ったまま死ねたほうが幸せだったかもしれない。 なのに知ってしまった。 問いただすべき人はもう誰も、いない。 何年に一度か、飛び切り機嫌のいい日に。 母から菓子をもらった記憶。 弟と遊んでいるのに追い払われもせずに 「夏樹さんもおいでなさい」 かすかに笑った顔。 手を伸ばせば叩かれる、そう染み付いてしまった俺の頭をそっと撫でる白い手。 一瞬あとにはまた叩かれるとわかっていても。 「……」 母上。 そう呼びそうになって、戸惑う。 俺は母を呼ぶべき言葉を持たなかった。 人前で「母上」と呼ぶ、余所行きの言葉しか持たなかった。 弟のように「お母様」と、甘えた事がなかった。 無意識に手が肩の古傷をつかむ。 痛みはしていない。 むしろ。 ――どこが痛いのか、俺にはわからなかった。 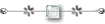
千尋を暴力で屈服させ、夏樹が生まれた。 「誰にも望まれない子供を作ることになる」 薫さんはそう言った。 確かにそれは間違いのないことだった。 千尋は身重の間中、無茶をしてばかりいた。 体を労わることなどしようともしない。それどころか積極的に痛めつけようとしていた。 私は言った。 「跡取さえ産んでくれたら後は好きにして構わない」 と。 千尋の行状は見る間に改まった。 彼女付きの小間使いに聞かされたところでは体内に育つ「旦那さまの血の入ったもの」に日々千尋はうなされ苦しんでいたそうだが。 私は聞く耳持たなかった。 仮に見舞えばより一層ひどくなるのは目に見えている。 互いに偽善だとわかっていることをしてなんになろう。 千尋に接触しない、それが私に残された、千尋にしてやることのできるただひとつの労わりだった。 そんな千尋の状態は見る見るうちに屋敷に充満し、伝播し、そして誰からも望まれない子供が生まれた。 いや。 待ち望んではいた。 私は待っていた。 千尋の出産を今か今かと待ち望み、苛々と部屋を歩き回った。 妻の体を案じる夫に見えたのだろうか。 わずかの間、空気が緩む。 その瞬間、誰かが 「男のお子様にございます」 そう伝えた瞬間、間違いなく私は歓喜に震えた。 待望の知らせに両の拳を震わせ、握り締め、天さえも仰いだ。 これで薫さんに逢える、と――。 使いの男は知った顔だった。 以前、薫さんの手紙を届けにきた。 その男がまたするすると屋敷に忍び込んでは私に手紙を渡していった。 見まごう事のない薫さんの字。 取るもの取らずに飛び出したのは、言うまでもない。 およそ一年ぶりでまみえた薫さんは少しやつれて、けれど狂おしいほどの笑顔で私を迎えてくれた。 夏樹よ、お前は覚えているだろうか。 薫さんは不思議とお前に会いたがった。なぜだかは今もってわからない。 私の血を引いたものに会いたがった――そう想像してみたりもするがしっくりとはしない。 はじめはそうだったのかもれない。ただお前に会ったあと、単純にお前を気に入った、それだけのことかもしれない。 薫さん。 なぜあなたは私を残して逝ったのか。 こんなにも知りたいことがたくさんある。あなたは私に不思議だけを残して独り逝ってしまった。 私は少年・青年時代を通して、一人で出歩くのを好みはしなかった。 薫さんは違った。 時には使用人の目さえも盗んでふらりどこかに歩きに行った、と聞く。 夏樹よ、覚えているか。 お前といつか二人で食べに行ったカリーライスの味を。 父がこんな所を知っているのは不思議だ、そんな顔をしていたお前が目の前に運ばれてきたカリーライスに心奪われた顔。 私は忘れられないでいる。 お前への愛情ゆえにではない。 はじめて薫さんと外食をした日の私はきっとお前と同じように驚いたことだろう、そう思う記憶ゆえに、だ。 私を連れ出した薫さんは 「なかなか良い味ですよ」 そう笑って私を見ていた。 それがどこで、なにを食べたのか惜しい事に私は記憶していない。 薫さんと過ごす時間の幸福さに――ただそれだけに酔って酔って酔い尽くしていた。 このまま命尽きるその日までともに過ごせると、そう信じていた。 私は、愚かだった。 |
モドル ススム